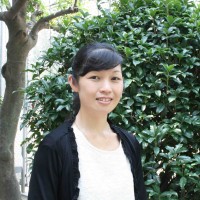鏡餅の由来と仏壇の飾り方

お正月の準備はいかがでしょうか。家の門の前に飾るのは、竹と松を用いた門松ですね。門松は年神様を家へお迎えする目印であり、降臨する依り代になるとされています。このようにお正月の飾りには一つひとつ意味があるので、それらを知って玄関やリビングを演出してみませんか?

鏡餅は、年神様へのお供え物です。「鏡」と呼ばれるのは、三種の神器にもある昔の鏡が青銅製で丸い形をしていたからです。鏡餅の飾り方は三方に半紙を敷いて、裏白(シダ植物で裏が白い)を乗せ、大小のお餅を二つ重ねて置きます。その上に串にささった干し柿やスルメ、ダイダイ、昆布などを飾ります。地域によって、お餅を紅白にするなど異なる伝統があるようです。最近は真空パックの鏡餅がセットで販売されているので、ずいぶん手軽になりました。神様のお供えなので、仏壇に鏡餅を飾る必要はありませんが、ご先祖様に新年の挨拶をする時、お正月飾りがあると気持ちも新たになると思います。

鏡餅は、12月28日から1月11日まで飾ります。28日は、「八」の文字が末広がりで、1月11日は「1」が揃っているゾロ目、どちらも縁起の良い数字だからだそうです。お供えから下げた鏡餅は「鏡開き」と言って、食べやすいサイズに切り分けて、お雑煮やお汁粉にして食べます。年神様にお供えした鏡餅にはパワーが宿っているので、美味しく頂きながら力を授かって一年の無病息災を願うと良いでしょう。
京都の職人が一つひとつ手作りしたちりめん細工の鏡餅はいかがですか?食べられないのが残念なほど、かわいい出来栄えです。毎年飾れるので経済的と人気があります。
ちりめん飾り 鏡餅

京都の職人が一つひとつ手作りしたちりめん細工の鏡餅はいかがですか?食べられないのが残念なほど、かわいい出来栄えです。毎年飾れるので経済的と人気があります。
ちりめん飾り 鏡餅


ギャラリーメモリアでは、鏡餅の形をしたキャンドルやお正月飾りの造花、ちりめん飾りなどを取り扱っています。小さくてかわいいので手土産にも最適です。お供えについて、もっと知りたい方は関連記事をご覧ください。
関連記事:お供え膳の意味と正しい置き方
関連記事:ご飯はいつお供えするの?浄土真宗の盛り方は?
また、仏事の疑問や悩み事がございましたら、お近くのギャラリーメモリアにご相談ください。

関連記事:お供え膳の意味と正しい置き方
関連記事:ご飯はいつお供えするの?浄土真宗の盛り方は?
また、仏事の疑問や悩み事がございましたら、お近くのギャラリーメモリアにご相談ください。
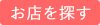
よみもの


2017年12月27日

無料カタログのご案内

画面上ですぐにご覧いただけるデジタルカタログと
無料でお届けするセレクションカタログの
2種類をご用意しました。
住まいに合う仏壇選びに、ぜひご利用ください。
■お電話でのご請求
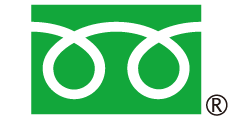
(受付時間/午前11時~午後6時 年末年始は除く)
- このコラムについては
-
八木研の広報企画室勤務。働くママ目線で、お客様の役立つ情報を発信していきたいです。